「ガンディー・ナース」
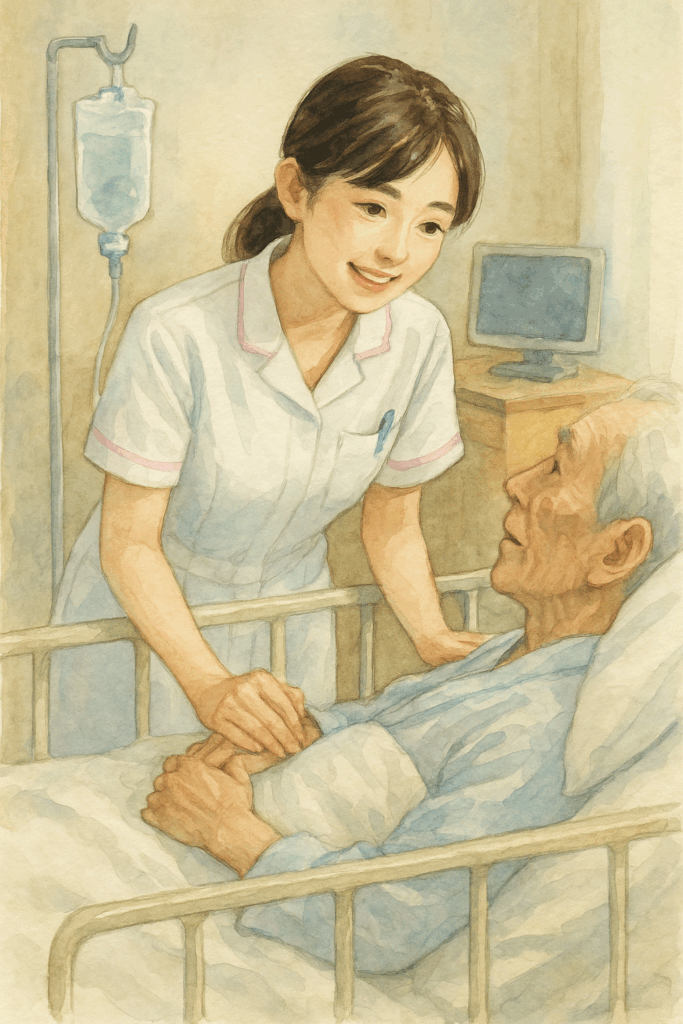
プロローグ
この小説はフィクションです。
ただ、私が聞いた話などを想像で膨らませて、フィクションの設定の中で書きました。しかし、内容に出てくる志や看護観、そして患者に向き合う精神は、どの病院にも居る「葛藤しながら正しくあろう」とする看護師さんの心そのものだと確信しています。
これを読んで勇気づけられる人が一人でも多くいることを祈っています。頑張れ!現場で命を守るナースたち!そして挫けないで。
どんな社会にあっても決して勇気を忘れず、しかし暴力や謀略にくみしないで、誠実に現実に向き合っている人に幸多かれと願ってやみません。
本編
第一章「白衣と霧」
五月十日 午前五時三十二分。 埼玉県の郊外に建つ医療法人送風会「清祥総合病院」は、深い霧に包まれていた。梅雨入り前のこの時期にしては異様な濃霧で、救急車のサイレンが遠くからかすかに響いてくるのが、霧に吸い込まれてなおさら不穏な気配を醸し出していた。
その朝、ナースステーションの蛍光灯の光が無機質にデスクを照らすなか、当直明けの看護師・瑞乃葵(みずの・あおい)は患者の記録をまとめながら、微かに眉を寄せていた。筆記用具が指先に馴染んでいても、心までは落ち着かない。どこかおかしい……そう思わせる空気が、数日前から病棟全体を薄く覆っていた。
「搬送来るって、男性、70代。意識レベルJCS200、呼吸微弱、たぶん腹部疾患」
ナースコールを中断して顔を上げたのは、若手看護師の佐久間利恵だった。昨年准看から正看になったばかりの彼女は、やや興奮気味に言葉を重ねる。
「さっき救急から連絡ありました。救急車5分以内に着きます」
「分かった。酸素と吸引の準備お願い。ストレッチャー、エレベーターホールに出しておいて」
葵は素早く指示を出し、自らは急患室へと向かう。
ストレッチャーに横たわっていた男性患者は、西岡雅信と名乗るも、意識は朦朧としていた。顔面蒼白、腹部は板のように硬く、体温も低下している。腹膜炎か、あるいは穿孔性の疾患だ。葵の脳裏に数パターンの緊急オペ対象がよぎった。
その場に現れたのは、外科医・川村崇だった。四十代半ば、癖のある口調とプライドの高い態度で知られているが、腕は確かだ。
「スキャン入れる前にCT行くぞ。こんなもん、画像診るまでもねえが、エビデンスが必要だ」
ぶっきらぼうに言い捨てると、川村は診療録に乱暴な文字を走らせた。付き従うレジデントは無言で頷く。
CTの結果は、十二指腸穿孔。急を要する状態だった。
「オペ台、今動けるな?」
「第二が空いてます。麻酔科にも連絡済みです」
葵の言葉に、川村は小さく頷いた。
「オーケー。30分以内に切るぞ。患者の家族には?」
「ご家族には私が対応します」
霧の中、タクシーで到着したのは娘だという女性だった。50代に差し掛かるかどうかの年齢で、葵の言葉を聞くなり、両手を合わせて頭を深く下げた。
「父を、どうか……お願いします」
手術のリスク、合併症の可能性、術後の集中治療について、葵は丁寧に説明し、IC(インフォームドコンセント)を行った。すべてを受け止めたその娘は、一言だけ、「お願いします」とだけ繰り返した。
緊急オペは無事に終了した。
午後に入り、葵はナースステーションで患者の記録をまとめていた。そこへ、別の看護師が話しかけてきた。
「瑞乃さん、あの急患の対応、すごかったって救急隊の人たちが褒めてましたよ」
「……そう? ありがとう」
嬉しさはあったが、葵は浮かれた様子を見せなかった。心のどこかで、静かな不安が燻っていた。なにかが、おかしい……病棟の空気そのものが、微かに軋んでいた。
それは単なる忙しさのせいではなかった。ナース同士の会話の温度、患者への声掛けのトーン、医師とのやり取り。そのすべてが、かすかに“ずれて”いるように感じられた。
その日の夜、休憩室で佐久間と話していた葵は、ふと佐久間の沈んだ表情に気づいた。
「……なにか、あったの?」
「いえ……実は、昨日の夜勤のとき、患者さんの点滴、一本落とし忘れた人がいて……でも、それが私のせいってことにされてて」
「えっ、それ本当?」
「たぶんです。でも……主任に言っても、“准看の記録は信用できない”って……私正看になったのに……」
葵は言葉を飲み込んだ。
霧は、夜になっても晴れなかった。病棟のなかにも、霧のような曖昧で湿った空気が立ち込めていた。
それが、この病院の“日常”であるかのように——。
翌朝、ナースステーションに現れたのは、新しく配属された看護師・平井遥だった。おっとりした笑顔と、すっと伸びた背筋。新人らしい緊張と、芯の強さを併せ持つ印象だ。
「今日から外科病棟に配属されました、平井です。よろしくお願いします」
「こちらこそ。分からないことがあったら、遠慮なく言ってね」
葵がそう声をかけると、平井はほっとしたように微笑んだ。
そのとき、葵の背後から聞こえた声。
「新人のフォロー、よろしくね。葵さんは患者受けも良いし、丁寧だから、うちの顔みたいなものよ」
そう言ったのは主任の白鳥美沙子だった。
一見、明るく人当たりのよい白鳥主任。しかしその裏に、葵は説明しがたい“何か”を感じ取っていた。それは直感に近い違和感。笑顔の裏に、計算と探るような視線が潜んでいる気がしたのだ。
午後、葵は西岡の病室に足を運んだ。
「こんにちは。体調はいかがですか?」
西岡はまだ本調子ではないものの、意識ははっきりしていた。
「……お嬢さんかい。あのとき、顔がぼんやり見えてたよ。ありがとうな……命拾いした」
「いえ、私一人の力ではありません。皆で処置したんです」
そう言いながら、葵はゆっくりと血圧計を巻いた。
「ただ……何か気になることがあったら、遠慮なく言ってくださいね」
そのとき、西岡はほんのわずかだが目を細めてこう言った。
「……あの夜、点滴が一本ぶら下がってたんだ。けど……朝にはなかった。不思議だったよ」
葵の手が、ぴたりと止まった。
——まさか。 彼女のなかで、一つの点が線になろうとしていた。
第二章「沈黙のカルテ」
ラウンド明けのナースステーションは、朝の喧騒を経て、ほんの束の間の静寂に包まれていた。記録を書き終えた看護師たちがそれぞれの休憩に入り、空気の密度がゆるやかにほどけていく時間。だが、瑞乃葵はモニター前に座ったまま、記録を見つめていた。
西岡雅信の術後記録、バイタル、点滴投与履歴、処方歴。
「……やっぱり、おかしい」
声に出したわけではなかった。だが、疑念は確実に形をとり始めていた。
術前夜に投与予定だった抗生剤の一本が、電子カルテ上には“実施済み”と記載されている。だが、西岡本人は「点滴が朝には消えていた」と話していた。単なる記録ミスなのか、それとも。
「葵さん、まだ残ってたんですか?」
ふいに声をかけてきたのは、外来看護師の西原道子だった。30代前半ながら看護師歴は長く、落ち着きと洞察力を備えた人物だ。
「うん……ちょっと気になる記録があって」
「西岡さんの件?」
一瞬で核心に触れてきたあたり、やはり只者ではない。
「……みっちゃん、正直に言うと、点滴の記録と患者の証言にズレがあるの。誰かが“やってない処置をやったことにしてる”可能性がある」
「誰かが……“隠してる”?」
「まだ断定はできない。ただ、見過ごせない」
道子は一呼吸置いてから、静かに言った。
「私が確認してみるわ。点滴の管理表は紙で保管されてるものもあるから。病棟のストック室にあるはずよ」
葵は深く頷いた。道子なら、下手なことをせず冷静に状況を見極めてくれる。心強い協力者だった。
その日の午後、葵がナースステーションに戻ると、見慣れぬ顔が1人いた。白衣をきちっと着こなした長身の男性が、主任の白鳥と何やら話していた。
「今日から正式に配属になった田中さん。前の病院では急性期の外科病棟で勤務していたそうよ」
白鳥主任が紹介した。
「よろしくお願いします。田中圭吾です。経験はそこそこありますが、ルールとか雰囲気とか、学ばせていただきます」
田中は40代、目つきは鋭いが、声には誠実さがにじんでいた。
名札には「埼玉中央医療センター→清祥総合病院」と小さく記されていた。
(あの病院から?……なぜ、転職したんだろう)
葵は気になったが、口に出すことはなかった。
翌日の夜勤、休憩室でコーヒーを飲んでいた葵の隣に田中が腰を下ろした。
「瑞乃さん、ひとつ聞いてもいいですか」
「なに?」
「この病棟、何か妙な感じ、しませんか」
葵は言葉を詰まらせた。彼も同じ違和感を抱いている。
「正直に言えば、最近……記録と実態が合っていない場面が続いてる。あなたも気づいた?」
田中は頷いた。
「前の病院では、こういうズレが医療事故の火種になるって、何度も見てきました。だから……気を付けたいと思ってるんです」
その言葉に、葵は初めて彼の誠実さを信じられた気がした。
翌日の昼過ぎ、ナースステーションで書類を整理していた道子が、こっそりと封筒を差し出してきた。
「これ、昨日の点滴の記録。確かに“未実施”って手書きで残ってた。誰かが後からカルテだけ“実施済み”にしたのよ」
「……やっぱり」
その瞬間、何かがはっきりとした。誰かが、明確な意図を持って“改ざん”している。
だが、問題はそれだけではなかった。その手書き記録の欄外に、薄く消し跡が残っていた。
葵は不意に、白鳥主任の視線を思い出した。
(まさか……)
だが、証拠はまだ足りない。
その夜、田中と休憩室で再び会った葵は、慎重に言葉を選んだ。
「……ねえ、田中さん。あなた、どうしてこの病院に?」
彼は少し口元を引き締め、ゆっくりと答えた。
「実は……看護部長に頼まれたんです。ここの状況を“調べてほしい”って」
葵の目が静かに見開かれた。
「それって、つまり……スパイ?」
「そんな言い方されると、心外ですけど……でも、患者さんを守るためなら、なんでもしますよ」
言葉の裏に、強い決意があった。
霧の向こうに、うっすらと“真実”の影が見え始めていた。
そしてその影は、病棟のさらに深い“闇”を予感させていた——。
第三章「告発のカーテン」
初夏の陽射しが差し込むナースステーション。だが、清祥総合病院外科病棟の空気は、いよいよ重たく沈んでいた。
明らかになった西岡雅信の点滴記録改ざん。瑞乃葵と田中は、証拠を元に内部調査をすべきだと考えたものの、病棟内で動ける人間には限りがあった。中立的に動ける道子以外に、協力を仰げる人物は少ない。
そんなある日の午後、ナースステーションに新人看護師の平井が医師の元へ丁寧に挨拶をしている姿があった。配属自体はすでに済んでいたが、今日は正式な医師チームへの顔合わせの日だった。
「本日より正式に配属となりました、平井遥です。よろしくお願いいたします」
外科部長の川本敬三はやや疲れた笑みを見せながらも、静かに立ち上がり、白衣のポケットに手を差し入れたまま平井を見つめた。「新人か……昔は、挨拶ひとつにも覚悟がにじんでたもんだ」
低く穏やかな声に、年季の滲む威厳が宿っていた。
このやり取りを、葵はナースステーションの端から目にしていた。
(遥さん……この病棟で、うまくやっていけるかしら)
葵がそう思うのには理由があった。平井はおっとりとした印象のある女性だったが、どこか芯の強さを感じさせる一面もある。言葉選びは柔らかいのに、時に先輩看護師にも物怖じせずに意見を伝える姿は、周囲に「目をつけられる」リスクをはらんでいた。
昼休憩。スタッフルームに入ってきた道子が、静かに葵の隣に腰を下ろした。
「平井さん、ちゃんとやっていけるといいわね」
「そうね。でも、彼女にはきっと“強み”がある気がする。何か……芯のようなものを感じるの」
道子は、意味ありげに微笑んだ。
「……そうね。実は彼女、以前勤めてた病院で “ある事件”を経験したらしいわ。詳細は知らないけど、記録操作に関する内部告発をしたって噂」
「それで、うちに来たの?」
「たぶん、看護部長が選んだのよ。あの人……観察眼だけは鋭いもの」
葵は言葉を飲み込んだ。平井は、単なる新人ではない。この病棟で起きている“何か”を探るために、意図して配置されていた。——
その夜、瑞乃葵は自宅で看護記録を書くために残しておいたメモを見直していた。
(……やっぱり、おかしい)
西岡雅信の点滴記録。日付、時間、使用薬剤、署名欄。その全てが、彼女の記憶と食い違っていた。
翌朝、田中に相談したところ、彼も驚いた表情で画面を覗き込んだ。
「……これ、改ざんされてますよ。しかも瑞乃さん名義で」
「私が入力した内容じゃない。どうして……」
タイムスタンプは、葵が勤務していなかった時間帯に記録されていた。
「アクセスログは確認できますか?」
「できます。ただ……この記録操作、管理者権限が必要です。つまり、主任か、看護師長クラスでないと無理ですね」——
その日の夜、道子が息を切らしてやってきた。
「葵、記録室。今、誰かがシステムをいじってる……白鳥主任しか、いないはずよ」
急いで記録室へ向かうと、操作中の画面が開きっぱなしだった。そこには、瑞乃葵の名前で修正された複数の記録が。
そのとき、背後から声がした。
「……あなたたち、何してるの?」
白鳥主任だった。
田中が一歩前に出て答える。
「主任こそ、業務外の時間に記録操作とは、どういうことでしょうか」
「上の許可を得てやってる作業よ。疑うなら、看護師長にでも聞けば?」
不敵に笑う白鳥。
(誰か、バックにいる……)
葵は唇を噛んだ。記録の改ざんは、組織的に行われている。
そして、自分がその“標的”にされているのだ——。
第四章「霧の向こうへ」
週明けの月曜日、清祥総合病院の屋上には鈍色の雲が垂れ込めていた。瑞乃葵は、ナースステーションに入る前に深く息をついた。空気がどこか淀んでいる。それは天気のせいだけではない。見え隠れする記録改ざんの件、そして白鳥主任の不自然な行動。葵は確信していた。「これは、ただの“個人の不正”ではない」
その日、葵は外来の手伝いに一時的に派遣されていた。いつもは病棟勤務が中心だが、人手不足の外来は常に看護部からのヘルプを求めていた。
「瑞乃さん、こっちお願い!」
そう声をかけてきたのは、外来看護師の野本絵里。30代半ばの女性で、物腰柔らかく、的確な指示が出せるリーダー格だった。外来に異動して3年。病棟勤務経験も豊富で、スタッフからの信頼も厚い。
「こちらの患者さん、意識レベルが低下しています。直近の採血データを一緒に確認してくれますか?」
「はい」
葵が電子カルテに目を通すと、血糖値が異常に下がっていた。意識障害の原因は明白だった。
「低血糖……インスリン過剰か、あるいは自己注射ミス?」
「でも、患者さんは高齢で独居の男性。施設にも属していないし、インスリン処方も……出てないはず」
確認すると、やはりカルテにインスリンの処方はなかった。
「これ、誰かが外部から投与した可能性があるってこと?」
二人の間に、冷たい空気が走った。——
その患者、田代伸一(たしろしんいち)・76歳は、近隣の団地に住む無職の男性だった。認知機能にやや衰えはあったが、会話は成り立つ。独居であるため、地域包括支援センターが定期的に見回りに訪れていた。
「本人に聞いたら、『甘い注射を打たれた』って……何のことだろう」
葵が田代の手をそっと握った。
「田代さん、少しだけ教えてくださいね。注射をされたのは、どこで?」
「……うちの玄関でな。白い服を着た……看護婦さんみたいな人だったよ」
その瞬間、葵の中で警鐘が鳴った。白い服。玄関。高齢者へのインスリン投与。何かがおかしい。
夕方、葵は道子にこの出来事を伝えた。道子は一瞬顔をこわばらせた。
「それ、もしかしたら……以前にも似たケースがあったかもしれない。私がいた別の病棟で、糖尿病じゃない患者が急に昏倒して、原因不明の低血糖で運ばれたの」
「調査はされたの?」
「ううん、結局“患者の体質”ということで処理されたわ」——
その夜、葵は帰宅後、夫の卓也と愛娘二人と夕食を囲んでいた。
「今日も、何かあった?」
「うん……また、不思議な症例があって」
卓也は箸を置き、真剣な顔で葵を見た。
「それは、偶然じゃないかもよ。何かパターンがあるなら、記録していった方がいい。あと……関係する人物の名前、共通点、場所や時間も」
「……うん、ありがとう」
その助言を受けて、葵は自室に戻り、小さな手帳にメモを書き始めた。
- 田代伸一(低血糖)
- 玄関口、白衣の人物
- 処方なし→外部投与の可能性
- 類似事例:道子の証言
翌日。病棟の看護師・佐久間がこっそり葵に耳打ちした。
「昨日、白鳥主任が“往診データ”を持ち帰ってたって聞いたんです」
「往診? うちは往診担当制じゃないはず……」
「ですよね? それで気になって」
また、ひとつ、靄が深まった。
白鳥主任の行動、未解決の患者の異常症例、そして看護部長の意図的な人事配置。
すべてが、どこかで繋がっている——。
そして葵の心に、また一つ確信が芽生えた。
“これは偶然ではない”
“誰かが何かを、隠している”
梅雨雲の向こうで、誰かが笑っている。
第五章「静かな目撃者」
水曜日の午後、清祥総合病院の外来待合室はいつもより人影が少なかった。コロナ明けの初夏、地域の感染者数がようやく落ち着きを見せはじめていたが、通院を控える高齢者はまだ多い。瑞乃葵は、ふと受付カウンターに目をやった。
「……あの人、また来てるわね」
そこにいたのは、先日インスリン過剰で搬送された田代伸一の隣人を名乗る中年女性。名前は間宮冴子(まみやさえこ)、60代前半。田代の搬送後に「心配で」と毎日のように病院を訪れては、スタッフに詰め寄るような態度をとっていた。
「本当に、あの人に面会させてもらえないの? 私、救急搬送された日の夜に、話があるって頼まれてるのよ」
葵は野本絵里と目を見交わした。
「ちょっと確認してみますので、少しだけお待ちいただけますか?」
応対した受付のスタッフが対応に困った表情をしていたため、葵がその場をおさめに入った。——
その後、ナースステーションで患者リストを確認したが、田代の状態はまだ安定しておらず、一般面会は制限中だった。だが、その日最後のカンファレンスで、医師のひとりが不意に口を開いた。
「今日、午後の検温時、田代さんが『もう注射はいやだ』と何度も口にしていたって報告があった。誰かの入れ知恵か、脅されていたのかもしれないな」
葵の背筋が凍った。
「脅されて……それは、冴子さんのことですか?」
「わからん。でも、彼女の言動は少し気になる。身内でもないのに、異常に執着している」
その日の夜、葵は外来から病棟へ戻ると、田中が休憩室で資料をめくっていた。
「瑞乃さん、ちょっと見てください」
田中は葵に数枚の紙を差し出した。それは院内で共有されたヒヤリ・ハット報告の抜粋だった。数ヶ月前、似たような事例が何件も上がっていた。
- 高齢患者の突然の意識障害
- 原因不明の血糖値異常
- 外来帰宅後の転倒事故……
「全部、発生曜日が水曜日か金曜日なんです。しかも、午後」
「偶然じゃないかもしれないわね」
「そして、その時間帯に限って、往診記録がなぜか白鳥主任のIDで電子ログインされてるんですよ」
「白鳥主任が……?」——
翌朝、葵は意を決して、事務長の宮坂晴信に相談することにした。
実は、数日前から、事務長は口が堅く信用できる人物だから、一度相談してみた方が良いと道子に熱心にアドバイスされ、自分の心を守るためにも一度話をしてみる事にしたのだ。
事務室のソファに腰をかけた葵を見て、宮坂はいつもの柔らかな表情を崩さずに言った。
「話してごらんなさい。私は、事実だけを聞きますから」
葵はこれまでの出来事、田代の搬送、冴子の奇妙な面会要求、白鳥主任のID使用、すべてを伝えた。宮坂は黙って頷き、時折メモをとる。
「……白鳥主任のIDでのログ。これはセキュリティチームにも協力を求めた方が良いでしょう。もし彼女が不在の時間帯にも使用されていたなら、不正アクセスの可能性もあります」
「はい、田中さんとも確認を進めています」
「瑞乃さん、ひとつだけ忠告します」
宮坂の目が、普段の柔らかさを潜め、鋭く光った。
「真実を追うとき、必ず敵も増える。正しさは、必ずしも力にならない。だけど……それをやり切った先にしか、本当の仲間も現れない」
葵は、静かに頷いた。
この日以降、瑞乃葵は、ただの“看護師”から、一歩前へと踏み出す覚悟を固めた。
小さな事実、小さな不信、静かな目撃者——
それらが一つに繋がる時、清祥総合病院の闇が、ゆっくりとその輪郭を現しはじめる。
第六章「罠の残響」
朝霧が晴れぬまま迎えた午後、清祥総合病院の外科病棟は奇妙な静けさに包まれていた。窓から差し込む薄い光がナースステーションの床を鈍く照らしている。瑞乃葵は、端末に表示された患者データを睨みながら、まぶたの奥に刺さるような頭痛を覚えていた。
「田代洋一さん、また微熱が上がっています。38.4度……それと、浮腫も少し増えているようです」
モニター越しに、平井遥が報告する。葵は即座にカルテを引き、今朝の点滴と血液検査の内容を見直す。
「抗生剤の量……ん? おかしい」
点滴の内容が、処方箋とわずかに異なっていた。正しくは1000mg投与のはずが、点滴バッグには“1500mg”と記されていた。
「確認する。平井さん、さっき薬剤を準備したのは誰?」
「それが……私が準備しようとしたときには、すでに準備されてました。冷蔵庫から出されていて、薬液も混合済みだったので、そのまま……」
「誰が?」
「たしか……ログを見てください」
葵は端末で薬剤管理記録のログを開いた。そして、そこで見つけたのは、見慣れたIDだった。
“ST0731”――白鳥主任のログインID。
「……でも、白鳥さんは病欠中のはずよね?」
白鳥主任は記録室であって以降、顔を合わせていない。理由は定かではないが病欠と申請されており、看護師長からそのように説明があった。
「そのはずです。でも、記録は2時間前。朝の6時15分です」
葵の背中に冷たい汗が流れた。
ナースステーションは朝の引き継ぎを終え、静まり返っていた。だがこの“静けさ”の中で、何かが確実に動いている。
午後3時過ぎ、葵は休憩時間を使って記録室に向かった。
静かな部屋の中、薄暗い蛍光灯の下で、彼女は10日前の田代の入院記録を読み返していた。担当看護師欄に、何度も繰り返し“ST0731”が登場している。
「体調を崩す前から、白鳥さんがこの患者に頻繁に関わっていた……?」
そのとき、ふいに後ろから声がした。
「葵さん、まだ調べてるの?」
振り返ると道子が立っていた。手にはコンビニのビニール袋を下げ、買い物帰りのようだった。
「ええ、少しだけね。……道子さん、白鳥主任のIDって、誰でも使えるものなのかしら?」
道子は少しだけ首をかしげた。
「個人パスワード付きのIDだから、基本的には本人しか使えない。でも、可能性がゼロとは言い切れない。昔は共有端末で自動ログインのままのこともあったから……」
「今は?」
「最近は厳しくなってる。ログインのたびに顔認証が追加されているから、本人以外が使うのは難しいと思う」
葵は、天井の明かりを見上げながらゆっくり頷いた。
夕方の申し送り。看護師長の姿はなかった。代わりに日勤リーダーの瑞穂梨沙が仕切る中、葵は静かにその場に立っていた。瑞穂は黒髪で着飾るタイプではないが、逆にシンプルな身なりが、実年齢よりも若く見せている。看護師長や主任とも適切な距離を保ちつつ、いつも中立な立場で物事を見ることができるので、若手看護師からは人気があった。
「田代さん、今日の夕方の採血で、クレアチニン値が2.9まで上昇しています。明らかに急性腎障害の兆候です」
医師の笠原尚人が首を傾げた。「抗生剤の副作用かもしれないな。内容、再確認しといて」
「……もう一度、投与記録を確認します」
ナースたちはそれぞれ控えめに頷いたが、誰の顔にも明確な焦燥が見えた。
「頼むね!」と笠原は後頭部の髪をワシワシとかき上げながら呟くように言った。周囲の雰囲気を察知しているのだろう。ただ患者さんのことを心配している姿を周囲の看護師は理解していた。
夜、病院の駐車場で一人、葵は夫の黒いミニバンの助手席に乗り込んだ。温かいコーヒーの缶を渡された。
「……また何かあったんだな?」
彼はそれ以上問わず、ただフロントグラスに視線を向けたまま言った。「どう考えてもおかしいことがあるなら、まずは“見える形”で確かめてごらん。感情を抜いて、事実だけを見つめて」
「見える形で……」
葵は夜空を見上げた。濃霧のように覆い尽くすこの病棟の“何か”を、まず明るみに出す。それが今の自分にできる唯一のことだと感じていた。
翌朝、葵は意を決して事務長の宮坂を訪ねた。
「田代さんの投与記録に不審な点があります。白鳥主任のIDが複数回使用されていますが、本人は病欠中です」
宮坂は驚くことなく、淡々と返した。
「その記録、今すぐコピーを取ってもらえますか?」
「はい」
「私の方でも調べます。ただし、これを公にする場合、あなたも相応の覚悟が必要です」
「わかっています。私は……患者のために動いているつもりです」
宮坂は柔らかく頷いた。
「あなたのような人間が残ってくれていることが、この病院にとっての唯一の救いかもしれません」
冷たい廊下を戻る途中、葵はふと、ナースステーションの奥から誰かの視線を感じた。
ふと振り返るが、誰もいない。ただ、壁の向こうから何かがこちらを見つめているような、そんな感覚だけが残った。
——何かが、蠢いている。
清祥総合病院の白衣の奥で、まだ見ぬ“顔”が、静かにこちらをうかがっていた。
第七章「ナースコールの沈黙」
深夜二時、病棟はまるで海の底のように静まり返っていた。
瑞乃葵は、ナースステーションのモニターに目をやりながら、患者のナースコール履歴を確認していた。前日、三号室の田代洋一が発熱と嘔吐を繰り返し、明らかに症状が悪化していたにもかかわらず、カルテには特記すべき異常の記録がなかった。
だが、葵の記憶には残っていた——あの夜、コールが鳴っていたはずだ。
「ログ、あるわね……二時十三分、三号室。反応時間……なし?」
システム上では、誰も応答していなかったことになっていた。
「そんなはずない……平井さん、あの夜は?」
夜勤担当の平井遥は見回りから帰ってきて、デスクにもたれ掛かっていた。
「……私、遅番だったんですが、気づかなかったんです。でも、確かに一瞬だけ“誰か”の声を聞いた気がして……夢かと思いました」
若い平井看護師は、言葉を探すようにしながら続けた。「その声、白鳥主任に……似ていたんです」
葵は視線を伏せた。頭の中で警鐘が鳴る。病欠中であるはずの白鳥が、まるで病棟のどこかに“存在”しているかのような錯覚。
——いや、錯覚ではないのかもしれない。
午前四時、救急搬送で運ばれてきた新たな患者が一時的に葵たちの病棟に預けられることになった。名前は朝比奈圭一。70代の男性で、意識は混濁し、受け答えも曖昧だった。
医師の笠原が診察を終えると、葵にそっと言った。「この人、たぶん……以前にも入院してた。見覚えがある」
カルテを照合すると、確かに十年前の記録にその名前があった。だが、診療記録は途中で切れていた。
「この病院を“出た”のか、“記録が消された”のか……」
笠原の目は鋭かった。その裏に、何かを隠すような緊張が走っていた。
「彼は何か知っているのかもしれない。いや、覚えているとしたら……」
葵の背筋に、冷たいものが走った。
午前六時。申し送り前の短い時間に、葵は宮坂事務長と面会した。
「田代さんのケースですが、やはり何か操作されている可能性が高いです。白鳥主任のIDで投与準備された形跡が、また残っていました」
宮坂は一枚の紙を差し出した。ID操作ログの詳細だった。
「この紙、誰にも見せてはいけません。ただ、覚えていてください。これは“入り口”です。真実に迫るための」
「……白鳥主任は、本当に病気なのでしょうか?」
「診断書は提出されていますが、それが事実かどうかは……」
宮坂の言葉の先には、暗く深い井戸のような沈黙があった。
夜勤終わりの帰り際、平井が一通のLINEメッセージを葵に見せた。それは、グループチャットの切り取りを転送してもらった内容だった。誰に送られたものかまでは分からないようだ。
《昨日の深夜に主任から連絡が来ました。「誰にも言わないで。今、全部準備してるところだから。私が正しいことを証明する。必ず追い出してやる!」って……怖かった。震えました》
「平井さん、これを保存しておいて。いつか使うことになるかもしれない」
葵は穏やかに微笑んだが、その瞳には決意の炎が灯っていた。
翌日、田代の容態は一時的に安定していたが、突然心拍数が上昇した。
「除細動器、用意して!」
医師たちが駆けつけ、処置が施される。命は取り留めたが、原因不明の心拍異常。調べた結果、点滴のラインに、別の薬剤が混入していたことが発覚した。
薬剤庫にはアクセス記録が残っていた。
“ST0731”。またしても、白鳥主任のID。
夜、葵はナースステーションで独り、カーテンの隙間から病室を見つめていた。
田代のベッドサイドに、一瞬“誰か”が立っていたように見えた。
葵が駆けつけると、そこには誰もいなかった。ただ、シーツの端が微かに揺れていた。
ナースコールのボタンが、静かに点灯していた。
第八章「医局の静謀」
早朝、清祥総合病院の医局。薄曇りの窓の外から差す陽光が、静寂の室内に鈍く反射していた。
外科医の笠原尚人は、誰もいないブリーフィングルームでコーヒーを片手に電子カルテを確認していた。
「……また、白鳥のIDか」
彼は、田代のケースを見ながら独り言を漏らした。白鳥が病欠となって以降、なぜか記録に現れるID。しかも医師の指示に反する内容が、数件にわたって入力されていた。
笠原は知っていた。この病棟には、ずっと前から“不自然な力”が働いていることを。だが、それを声に出す者はいなかった。
——ある一件を除いて。
十数年前、内科病棟で一人の患者が急死した。当時、担当だった看護師は白鳥。その後、上層部は「心不全による急変」として処理したが、医局内には“違和感”が残り続けていた。
その時、葵の名前を初めて耳にした。
「葵さんて人が、記録に疑義を呈してきたんです。あれ、ちゃんと見ておくべきでしたよね」
かつての医局長の言葉が、今も耳に残る。
笠原は一つの決心をし、カルテからUSBにログデータを保存した。
その日の午後、葵は処置室で患者の包帯を巻き直していた。
田代伸一は、かすれた声でこう言った。
「……昔、似たようなことがあった。何も言えなかった」
「え?」
「看護師が、別の薬を入れた。俺、知ってた。でも、怖くて……言えなかった。誰が何をしたかなんて……病院が全部隠した」
彼の目は遠くを見ていた。葵は、その手を優しく握った。「大丈夫です。今度は、もう誰も隠させません」
夜、事務長・宮坂と笠原が密かに院内の小会議室で会った。
「田代さんのケース、あなたも確認したそうですね」
笠原は頷く。「白鳥主任のIDが使われています。薬剤ミス、もしくは意図的な混入の可能性がある」
「証拠は?」
「あります。ただ……院内にまだ協力者がいる」
宮坂は深く息を吐いた。「あの時の失敗は、もう繰り返せません」
翌朝、看護師長・大迫明日香が珍しく早朝から病棟に姿を現した。いつものような破天荒な笑顔を浮かべていたが、目の奥には張り詰めたものがあった。
「みんな、おはよう。今日も“全力で患者第一”ね!」
そう言いながら、葵の耳元で囁いた。
「事務長と医局、動き始めたわ。あなたの準備は、いい?」
急に言われた内容を計りかねて硬直した葵は、深く頷いた。「はい、大丈夫です。」語尾に力が入らない。
ナースステーションのモニターには、朝比奈圭一の容態が静かに表示されていた。
その裏で、何人かの人間が静かに動き出していた。記録を読み、過去を掘り起こし、失われた真実を炙り出そうとしていた。
そして、その中心には——瑞乃葵の姿が、確かにあった。
第九章「裏切りの光」
午前九時、ナースステーションには張りつめた空気が漂っていた。
瑞乃葵は、配膳を終えたばかりの手で記録用紙を片手にステーションに戻った。ナースたちはどこかソワソワしており、目が合えば微妙な沈黙が走る。
「……何か、あったの?」
平井が葵のもとに走り寄ってきて、小声で訊いてくる。
「たぶん、また誰か、何かをやらかしたのかしら」
その瞬間、ステーションの奥から大迫看護師長が現れた。
「皆さん、朝礼前にひとつ伝達事項があるの」
彼女の口調は明るいが、視線の奥にある光は冷たかった。
「昨日の田代さんの記録について、一部の処置内容が不適切だった可能性があります。……詳細は医局と事務が調査中。みんな、患者さんを不安にさせるような言動は控えるように」
その言葉に、ナースたちは息を呑んだ。
葵は、大迫の目をまっすぐに見た。
——まるで、すべてを知っているような言い方。
だが、それは味方の表情ではなかった。
午後、医局の笠原から一本の電話が葵に入る。
「大迫看護師長が、上層部に“誤処置の噂を広めているのは葵だ”と報告したらしい」
「……何ですって?」
「しかも、彼女は“新人看護師の証言によれば、瑞乃葵が看護部長のスパイとして病棟に潜り込み、職員の行動を密かに監視していた”と話していたようだ」
言葉を失った。
——スパイは、田中さんだったはず。
ではなぜ、自分が……?
その日の夜、田中と平井が葵を休憩室に呼び出した。
「白鳥主任が、あなたの名前を使って”改ざん”の証拠をでっちあげて、集めた証拠を提出したらしい」
田中の声が低く落ち着いていた。
「俺が集めていた資料や、平井が持ってきた記録、すべて“葵さんがやった”って筋書きにされてる。俺たちの存在は、完全に消される流れだ」
「そんな……どうして……」
平井が手を震わせながら言った。
「私たちがスパイだったってことも、全部隠して、葵さんを悪者にしてるの」
田中が続けた。
「白鳥主任と師長は完全にグルだ。上に報告したのも、たぶん仕組まれた話。看護部長もそれに乗っかってるが、やつには仲間はいない。誰のためでもなく、師長を潰したいだけみたいだから」
その夜、葵は事務長・宮坂の元を訪ねた。
「私は、自分から真実を公にするつもりはありません」
葵は迷いながらも、決意あるまなざしで話を切り出した。
「確かに私が持っている情報では、白鳥主任が主犯で、大迫看護師長もグルです。岩淵部長がスパイを送り込んでいたのも知っています。」
そこで一度話を切って、葵はなぜ自分がこのような決断をしたのかを思いめぐらしていた。数週間前に夫の卓也と一緒に見た「マハトマ・ガンディー インド独立の父」という映画の「無抵抗・不服従」というテーマが葵の心を強くつかんで離さない。白昼夢のようなこの回想は、葵の感覚では20分ほどあったように思えたが、数秒の出来事のようで、宮坂の声で意識が現実に引き戻された。
「瑞乃さん!どうしました?」
「はい!・・・それでも病欠で現場にいない白鳥主任の非難をしたところで、やっていることは相手と同じになってしまいます。私にはそんなことはできません」
宮坂は眼鏡を外し、深く息を吐いた。
「あなたのような人が、潰される病院に未来はありません。ただし、あなたの覚悟は尊重します。私は私のすべきことをします」
翌日、事務局に複数の告発書が届いた。そこには田中、平井、さらには患者家族や同僚数名の署名が添えられていた。
——白鳥主任の勤務記録の不審、
——患者の同意なき処置、
——瑞乃葵の名を騙った偽装報告、
——そして、大迫師長の裏取引と隠蔽の共謀。
第十章「告白の連鎖」
朝の光が清祥総合病院の外壁を黄金色に染めていた。
七夕の朝、空は晴れ陽光は強くなり始めていたが、病棟の空気は冷たく張り詰めたままだった。
瑞乃葵は、前夜ほとんど眠れなかった。
不安、怒り、失望。そしてほんの少しの希望。
心が重たく沈む中、それでも白衣の袖に腕を通すたび、胸に一本の芯が通るのを感じていた。
この病院で、正しいことを守りたい。
ただそれだけだった。
事務長・宮坂の主導で、内部調査報告書はまとめ上げられた。匿名の証言も含め、複数の患者や家族、職員の発言が一致していた。白鳥主任の虚偽報告、大迫師長との共謀、看護部長の組織私物化。
それらすべてが、瑞乃葵に罪を着せることで糊塗されようとしていた。
だが、ついに。
それを覆すだけの材料が、今、整った。
午前十時、会議室に看護部長、事務長、医局代表の笠原、外科部長の川本そして告発に関わった職員の代表として田中、道子が呼ばれた。葵は他数名の看護師と共に座っていた。
「本日は、看護部長・岩渕政男による一部人事操作と、看護師長・大迫明日香、および元主任・白鳥美沙子の行動についての最終報告を行います」
事務長・宮坂の声は静かだったが、会議室の空気は張りつめていた。
「岩渕部長は、過去に看護師長・大迫明日香とたびたび衝突しており、個人的な関係悪化を理由に、スパイを病棟に送り込むよう画策。その結果、田中看護師および平井看護師が“監視”の名目で配属されました」
葵はうなだれる田中の横顔を見た。彼の表情には、自責と無念が入り混じっていた。
「一方、看護師長・大迫明日香は、かねてより白鳥美沙子主任と親密な関係にあり、新人二名に対して過度な指導と心理的圧迫を行っていたことが複数の証言から明らかとなりました。更に白鳥主任は、瑞乃葵看護師を“情報漏洩者”に仕立て上げ、虚偽の報告を医局に提出」
宮坂がページをめくる音が響いた。
「以上の事実から、岩渕部長には看護部管理責任の不履行による更迭を、大迫看護師長および白鳥主任には懲戒処分を、それぞれ理事会へ上申し、承認されました」
一瞬の沈黙。
そのあとに、静かな拍手がひとつ、道子から起こった。
彼女の拍手に、田中が、平井が、他の同席者が続いた。
そして、葵も。
小さな、でも確かな希望の音。
数日後、大迫師長は正式に退職、白鳥主任も“体調不良”を理由に職場を去った。
岩渕部長は事務職へ異動。二度と看護現場に口出しすることはなかった。
春の風が吹き抜ける外科病棟の中庭。
「もう一度、やり直していいんでしょうか」
平井が葵に訊いた。
「いいに決まってるじゃない。ここからは、私たちの手で作っていく病棟よ」
葵が笑って応えた。
廊下の先で患者がナースを呼ぶ声が聞こえた。
それは、かつて沈黙していたコールの音。
今は誰かが、確かに応えてくれる。
そして、その“誰か”のひとりである自分を、葵は誇りに思った。
終わったわけではない。
だが、確かに——始まりが来たのだ。
第十一章「陽のあたる方へ」
清祥総合病院、十月十日、秋。
小気味よく晴れ上がった秋の一日、爽やかな日差しが中庭のベンチに影を落としていた。
瑞乃葵は一歩、また一歩と、白衣の裾を揺らしながら病棟の廊下を歩く。その足取りには、これまでとは違う静かな強さがあった。
かつては怯え、孤独に押し潰されそうになっていたあの場所。
今、すれ違う同僚たちが、微笑みながら挨拶をくれる。
「おはようございます、瑞乃さん」
「今日のラウンド、手伝いましょうか?」
その一つ一つが、心に沁みる。
かつての沈黙は、確かに音へと変わり始めていた。
あの会議の後、葵は主任にならないかと宮坂に提案されたが、丁寧にお断りした。
「患者さんに関わっていたいんです。私はそのために看護師になったので」
笑顔でそう答える葵に、宮坂は眼鏡を人差し指で押し上げながら頷いた。
新たに主任に就任した道子は、午前のカンファレンスで職員全員に向かってこう話した。
「これまでのことを振り返るのは、簡単じゃない。でも、私たちは今、もう一度、初心に立ち返る時だと思っています。患者さんと、そして互いに、正直であること。誠実であること。それが、私たち看護師の原点です」
会議室に沈黙が落ちたあと、拍手がわき起こった。
あの薄暗い膜の張った病棟の空気が、ガラリと変わってきていた。
田中はと言えば、以前より口数が少なくなったように見えたが、その分、行動で示すようになった。
夜勤明けでもカルテの整理を手伝い、患者のちょっとした表情の変化にもすぐ気づいて声をかける。
「……見かけによらず、繊細なんだよな、田中さんって」
そんな声が、どこかのナースから聞こえる。
彼の存在が、確かに認められはじめている証だった。
平井は新人研修のサポートに回り、後輩に優しく声をかけていた。
「間違ってもいいの。大事なのは、そのあとどう動くか、だから」
少し前の彼女とは、まるで別人のようだった。
昼休み、葵は久しぶりに外来の道子と中庭で会った。
「空気、変わったね」
道子は風に髪をなびかせながら、缶コーヒーを差し出してくる。
「うん。人の目が怖くなくなった」
「あなたが最初に変わったからよ。人って、変わろうとする誰かを見て、初めて自分もって思えるの」
葵は缶のプルトップを開け、頷いた。
その夜、葵は久しぶりに家族とゆっくりと夕食を囲んだ。
夫の卓也は味噌汁を盛り付けながら言った。
「……最近の君は、言葉が穏やかになったな」
「うん。やっと……私の中で霧が晴れてきたのかもしれない」
「やっぱりな。君のやり方は間違ってなかったんだよ。時間はかかったけど、ちゃんと伝わった」
食卓には、久しぶりに笑顔が戻っていた。
翌朝。
廊下の先から患者がナースを呼ぶ声がする。
「看護師さーん!ありがとう、元気になったよ!」
葵はその声の主に微笑んで手を振った。
その横を、新しく配属された若い看護師が走っていく。
かつての自分と重なるその背中を見送りながら、葵は心の中で静かに言った。
——次は、私が育てる番だ。
病棟は、ようやく。
本当に、人のための場所になろうとしていた。
空気は澄み、光が差し込む。
瑞乃葵の物語は、ここからまた新たな一歩を踏み出す。
そして、静かに始まる——。
第十二章「そして、白衣は灯る」
秋も深まる早朝の清祥総合病院。
心持ち弱い陽光が病院のガラス窓に反射して、薄い金色のカーテンのように差し込んでいた。
瑞乃葵は、ナースステーションの隅でコーヒーを啜りながら、一冊の小さなノートを閉じた。
それは、ずっと書き続けていた個人的な記録帳だった。日々のヒヤリ・ハット、患者の何気ない言葉、仲間のちょっとした変化。声にならないものを、ずっと綴っていた。
「全部、終わったわけじゃない。でも……ここは、もう、かつての病棟じゃない」
そう思えた。
外科医の笠原が朝の回診を終えてナースステーションに顔を出した。
「瑞乃さん、例の薬剤確認の件、助かったよ。前より現場、締まってるな」
「ありがとうございます。みんなが、看護師として頑張っているだけです」
笠原は小さく頷き、資料を渡してきた。
「……一つ、伝え忘れてた。あの夜、君が記録してた点滴ミスのデータ、あれがなかったら重大な投薬事故になってた。俺も、見落としてたよ」
葵は驚いた表情を浮かべた。
「……そんな、大したことじゃ」
「いや、大したことだよ。君が残した記録が、この病棟を救った。あんたの“無言の行動”が、誰よりも響いてる」
その言葉が、心に深くしみ込んだ。
その日、久しぶりに夜勤だった。
病室を一つひとつまわる中で、葵は何度も患者から声をかけられた。
「看護師さん、いつもありがとうね」
「安心して眠れるの、あんたの声聞くと」
葵は、丁寧に枕を直し、水差しの水を替える。
それは、かつて誰かが彼女にしてくれたことでもあった。
夜勤の合間、ナースステーションで道子とすれ違った。
「なんか最近、若い子たちが瑞乃さんに べったりね」
「……ありがたいことに」
「でもね、あの子たち、あなたの背中をちゃんと見てる。葵、今、病棟の“軸”になってるよ」
そんな言葉を、かつての自分が聞いたら、きっと信じなかっただろう。
午前三時。
薄明かりの廊下に、ナースコールが静かに鳴った。
機械的な音に、葵は自然と身体を動かした。
患者の名前を確認しながら、扉をそっと開ける。
「……すみません、夢を見てたの。昔のこと。ちょっと、怖くなって」
年配の女性患者が、目元に手を当てながら笑った。
「大丈夫です。すぐ近くにいますから」
その一言で、患者はまた眠りについた。
葵はその姿を見届けてから、そっと扉を閉じた。
その一瞬 ――胸に灯るものがあった。
夜が明け、朝日がナースステーションを照らす頃。
田中と平井が出勤してきた。
「葵さん、おはようございます」
「お疲れ様です!」
「ありがとう。……今日も、いい一日になりそう」
三人の背後から、道子の明るい声が響いた。
「みんな、申し送り始めるわよー!」
清祥総合病院、外科病棟。今日もガンディー・ナース達の一日が始まる。
白衣をまとう人々の姿が、まるで灯りのように朝の光の中に浮かび上がっていく。
かつて濁っていた空気は、今ではすっかり澄み、
その中に確かに——
患者の命と心に寄り添うための、静かな灯がともっていた。
瑞乃葵の物語は、これで終わる。
だが、彼女のような看護師がいる限り、
今日もどこかで、白衣は灯り続けている。
