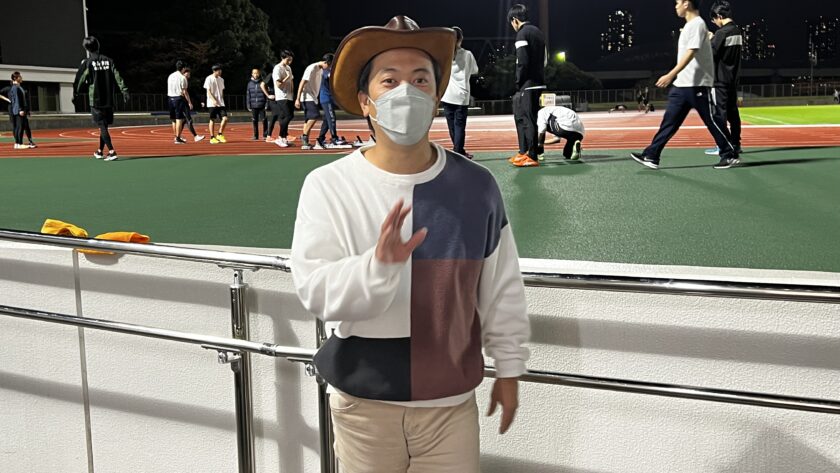第2回 2023年1月14日
変化を妨げるものは何か?会社が変わると困るのは誰?
変化って誰でも多少なりストレスを感じますよね。
例えば、自分の生活がルーティーン化している通勤など、いきなり遠くに行くことになって通勤手段や方向が変わると「ああ、せっかく覚えたのに・・・」とか思いません?そんなものだと思います。
わたしが工場の改革に着手した時のエピソードを紹介します。
一番最初に着手したのは生産計画表の作成でした。え?なんで?なかったの計画表?
と思ったそこのあなた!小さな町工場のような工場にそんな高等なものはありません。いやあるべきだったのでしょうが、それは職人たちの勘ピューターによって行われており、データが存在しなかったんです。
朝礼では1日の生産計画を・・・職人が発表していました。うん??誰も指示しないの?ってそうなんです。
注文を受け付ける時も納期は職人が決めているんです。ああ、これでは生産性は良くならないし、効率も良くならないよ!って思った私は、作業分担表を作って、1ヶ月の作業分担と製造枚数などの計画を作り始めました。
はい来ましたよ!文句が
「なんで今日この商品作る必要あるんですか?いらなくないですか?」
いやいや必要でしょ。あんたに何が分かるん?と思いましたが、丁寧に説明して動いてもらいました。
今考えればそうですよね。
いきなり現れた20代半ばの男が、30年間もやってきたやり方を変えようって言うわけですから。
みんなも「は?何言い出しているんだこの若造は!」ってなりますよね。
だから、私はこの変化を強要する傍ら、あることを始めました。
それは「機械の修理屋さん」です。
ミシンや工場で使う機械ってほんとよくトラブルんですよ。まあ、古い機械ってこともありますが、家庭用と違って動かしている時間や頻度、そして縫っているものの厚み、つまり負荷がとっても大きいんです。
ありがたいことに、私は昔から機械ものの修理をすることが多くて、ミシンも個人で持っていましたし、農業をやっていた傍ら、作業で破れたシャツの補修やジーパンの改造などをしていました。
その時の経験が役になったんだろうと思いますが、一番役に立ったのは「修理方法を知っていること」ではなくて、「構造を理解する方法」を知っていたことです。
JUKIやBrotherのミシンなどミシンは色々なメーカーがあり、構造もそれぞれなので、それを全て把握することなんてできません。縦釜や水平釜によっても構造は全く変わっってきます。
そんな無数にある機械の修理方法を全て理解し覚えることなんて私みたいな頭には到底無理。
でも、その打開策は、構造理解の方法なんです。どこから動力が伝わり、どこが動くから次はどこ・・・って言うような感じで、特に機械というのはその塊なんですよ。
さて話を戻します。
それをしていたらどうなったか?工場なんていうのは、今や機械が動かないとどんなにすごい職人も仕事になりません。その機械を制するものが工場を制すると言っても過言ではないのです。
そうです。みなさん20半ばの若者を無視できなくなっていったんです。無視できなければ、その指示も通りやすくなりますよね。そうやって製造の役割分担と生産計画を現場から管理者のもとに取り戻したと言ってもいい、第一次革命を行いました。

______________________
嫌われるんじゃないの?そんな革命を起こしたら。
______________________
その次の問題は、人間関係ですよね。
当然きついことをやって、現場を強制的に捻じ曲げた・・・今までのやり方を好き好んでいた人からはそう見えたでしょう・・・こんな自分物が好かれるはずはありませんよ。
でも、それは嫌われたくてやっているんじゃなくて、未来を守ろうとしてやっていることなんですが、日々の業務をこなす職人さんにはそんなことは「知ったこっちゃない」なんですよね。
そこで私が思ったのは「今好かれるか?今嫌われて将来慕われるか?」ということです。
なんせ、私の改革の刃は、その矛先は、目下の現場のみならず、本社の運営や経営陣に対する苛烈な批判にも向かっていたからです。
当たり前ですが、こんな激しいことをする前に、社長の言質は取りました。
「社長はこの会社を50年後も続けたいと考えていますか?それともあと5年持てばいいやと考えていますか?」それが私が言質を取った時の第一問でした。
なぜなら、50年先も続くようにと思うなら、このやり方してたら絶対にダメだったからです。
そこで、工場改革にあたる五カ年計画をたて、問題点を抽出し、優先順位をつけました。
はい!ここで言っておきます。
私は中小企業診断士の資格を持ってはいませんし、コンサル経験もありません。
企業再生のプロでもなければ、工場マネジメントの有識者でもありません。
しかし、ここではっきり言えるのは、誰が挑戦したところで、成功するかなんてみんな五十歩百歩。ポイントは、今目の前の問題を自分の課題として真剣に取り組めるか。ありったけの能力を解放して問題かけいつの糸口を見つけ出せるかだということです。
だから私は、A4のコピー用紙に何枚もブレインストーミングの要領でマインドマップを書き、ロジックツリーのように相関関係を明確にして問題点を探りました。
そうこの時、私は嫌われることを覚悟したのです。
だって、せっかく関わるなら、その会社が潰れることなく、逆に発展してほしい、未来の希望を掴めるようにしたいですもん!

______________________
商品を作れないお前に何が分かるの!?
って言われません?製造業の2代目!
______________________
これ、常々私が思っていることなんですが、製造業界の2代目とかってめちゃくちゃ大変ですよね。
だって、初代は実際に現場とか入って商品作りとかすること多いじゃないですか。そして二代目はだいたい子供、息子とかって、出来上がったものを受け継いでいきますよね。
工場でも同じことは起こります。初代の工場長が作ってきたものを2代目は受け継ぐんですけど、初代と一緒にやってきた職人さんは初代の工場長と同格かそれ以上に知識があったりして、2代目は完全にバカにされています!
そんな時私がやったのは、一番は前回同様、修理の傍らとにかく機械に触れること。慣れることです。
そして次に、新商品の試作を自分で作ることです。それは完全に新商品でなくても、例えばリニューアル商品でもです。だってこれはチャンスなんです。完全に出来上がった商品でなくてもいいんですよね!試作品なんだもん。
これからブラッシュアップしていけばいいんだから、クオリティーはそこまで細かく言われない。
そして、第三にやったことは、その開発商品の図面を自分で引くことです。
つまり、その商品がカタログ掲載されれば、公開されれば、その作り方は私に聞かないとわからない。
私のところに来ないと図面がない・・・そういう状態にしたんです。そうすると職人さんとの間に正しいコミュニケーションが始まります。バカにされている上から目線のやりとりではなく、「ここはどう作ればいいんですか?」「ここの裏側はどんな感じで仕上げればいいですか?」など情報を聞き出し、評価を確認するなどです。

______________________
従業員は家族だ。絶対に見捨てない!・・これはホント?
______________________
はい、これは神話です。フィクションです。
家族ではありません。
ですよね〜 そうなんですよ。
色々問題抱えた人もいます。その人たちを全て守って家族として過ごしていく。
そんな慈善事業していたら、会社は存続できませんよ。
ダメな時は、他の会社に行ってもらう。袂を分つ。
うちの会社が全世界で唯一の会社ならしょうがないですけど、会社は五万とあるし、その人に合った会社は他にあるはず。
だから転職を進めるし、当然問題が起きた時、それが会社のためにならない、周囲の従業員のためにならないときは即その方向で話し合いをしました。
厳しい、ひどいって思われるかもしれないですが、こういう問題は長引かせない方がお互いのためになります。
そして、従業員は家族ではありません。サービス残業や業務のなすりつけ、責任を不当に負わせることはあってはなりません。
ただし、契約によってその責務を全うしてもらうという姿勢を徹底的に打ち出しました。そうです。他の方は当たり前と思ったかもしれないですが、「雇用契約書」を整備しました。
それまで雇用契約書なるものはこの会社には存在しなかったからです。
そう!次に着手したのは法的書類などの人事関係書類の整備です。特に契約書は何度も作り直して、契約の内容が明記されわかりやすいように作りました。
面談の時は面談記録表、これは面談で聞くべきことを列挙してあり、質問内容の返答によって点数をつけ、合計点数によって合否を判断しやすくするものです。
面接官の好き嫌いで判断していないこともこれを見ればわかります。
さて次は、大急ぎで各所のマニュアルを作り始めました。
これが本当に時間かかりました。誰も読まないマニュアルをひたすら作るのは辛すぎるので、例えば1年に一回しか来ない商品の梱包の仕方のマニュアルや、ロープの通し方のマニュアルなど、
比較的みんなが使うだろうものから作りました。
大本命は「製造依頼書と図面」の没収です! はい?誰から?という声が聞こえてきそうですね。
そうなんです。当社の職人さんは今までの図面を各個人が保管していたのです。何十年分も・・・
はい!ありえない〜! と言ったそこのあなた!
日本の町工場的な工場の現状っていうのはそんなもんですよ。
指揮命令権のある人を明確にし、製造計画はそこから現場に指示を出す。雇用契約は書面で取り交わし、契約条件を明確にする。
給与や時給はわかりやすくスキームにして。人事の関連書類は・・・私が作った書類だけでも100は優に超えます。
そして肝心要の図面を職人さんから提出してもらい、ファイリングして大きな棚を作ってそこにいつでも閲覧できるようにしました。
さて、これでようやく工場らしい組織になってきたわけです。