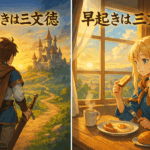2024年8月21日 第48回 モミーより(2024.8.7)
今日は江戸時代について話をします。江戸時代で長かったよなと思って調べてみると、265年間続いたそうなんですが、これ人が3、4回生まれ変わっててもおかしくないかなと思うぐらい長いですよね。
そんな江戸時代、幕府の政治は誰が将軍の座にあったとしても全く問題なく運営できるようにシステムを作っていたそうです。

それは一体どういうことかというと、将軍の役割はほとんど儀式化しており、将軍の口から出る言葉は5つだけで済んだそうです。
それは「それ」、「ちこ」、「良きに計らえ」、「そうせえ」「大儀」の5つです。
多くのようなドラマでもよく聞くような言葉ですよね。家臣が殿様に会う時は、最初から同じ部屋に入ることは許されていませんでした。
そこで、まずは初めに隣の部屋から将軍に挨拶をするわけです。
すると将軍は決まり文句である「それ・ちこ」というセリフを言うわけです。意味としては、隣の部屋からからでは聞こえにくいから、もっと近くに来なさいと言ったところです。
それに対して家臣はかしこまって「ははっ!」とお辞儀をして前に進むふりをするわけです。
ここで注意をしなければいけないのが、「ちこ」というのは結構トラップで、真に受けて、本当に将軍の近くに寄ってはいけません。
あくまでも前に進むふりをするのです。そのことで、あまりに恐れ多くて近くに進むことはできませんという態度を将軍に示すわけです。
結局、離れていて聞こえないから、老中といった側近が家来から聞いた話を要約して将軍に伝えたのです。

しかも、こうした報告や相談事に対しては、事前に老中や御三家たちの中で話がまとまっていることが 多いため、聞こえなくても全く問題がなかったわけです。
そして、話の内容がどんな内容であるあれ、将軍は重役たちが相談して取り決めをしたことに対して、形式的に了承をすれば良かっただけでした。その了承の時に言ったのが、「よきにはからえ」「そうせえ」だったわけです。
そして、最後に家来に対して言葉を「大儀であった」で締めくるわけです。
このように、どんな人がどのような立場になってもうまくいくように仕組み作りをしていくことが非常に重要かなと思います。仕組みづくりや人の成長はどうしてもトライアンドエラーの繰り返しだと個人的には思っています が、お互いが根気よく尊重し合って続けてほしいなと思っています。さて、今回の心がけは「謙虚に取り組みましょう」でした。 最近思うことは、自分の中と他人からの見え方はいいふうにも悪い風にも違うと思っています。
自分の中では「できている」と思っていることができていなかったり、「できていない」と思っていたことが成長していたり色々です。
ただ、それを真摯に全部受け止めて、指摘を受けたら広い心で見直し、褒められたら素直に喜びましょう。
ルーク工場長から

「そうせえ!!」素晴らしいメッセージ。ぐうの音も出ません。これが本当に20代の人のスピーチでしょうか。と言いたくなる出来でした。毎日朝礼でスピーチをして、皆大体10回くらいするとネタが切れてきます。しかし、周囲に興味を持ったり、日々の中でのできごとに注視することで、発見したことは人生において宝です。それをみんなに共有できる機会はより多くの人に与えられるべきだと私は思っています。