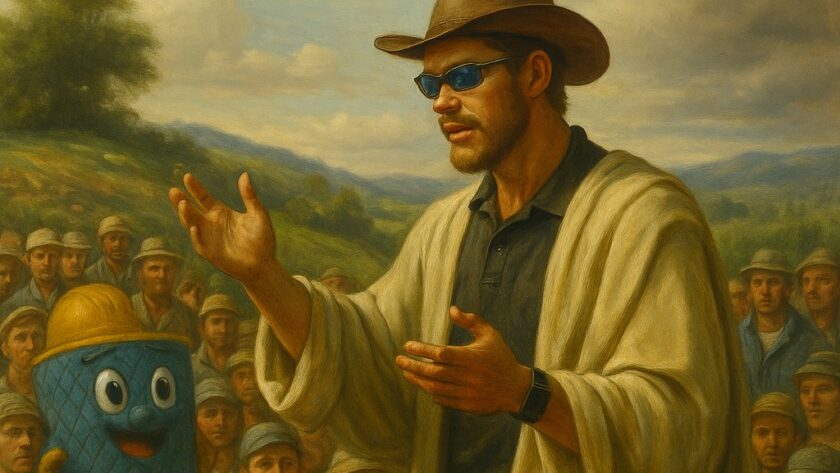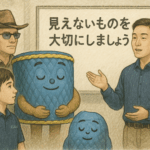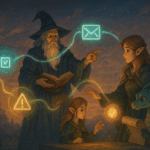2025.7.1 第69回 ルーク工場長から
私が朝礼の司会を担当するようになったのは、2012年6月。記録によれば、入社2年目のことでした。
それまでの朝礼は、当時60歳ほどの職人の男性が担当しており、その後は50代の管理職の方へ引き継がれました。そして私にバトンが渡ったのです。
ただ、当時の朝礼は、率直に言えば、混乱そのものでした。
出勤者と休暇者すら把握できず、今日の予定も明確でない。各人がその場で好きなように今日の仕事を話す。これでは生産の効率もスピードも管理職が調整する余地がありません。1週間、1カ月単位の計画も存在しないため、生産予測や納期の見通しすら立たない。そんな状態だったのです。
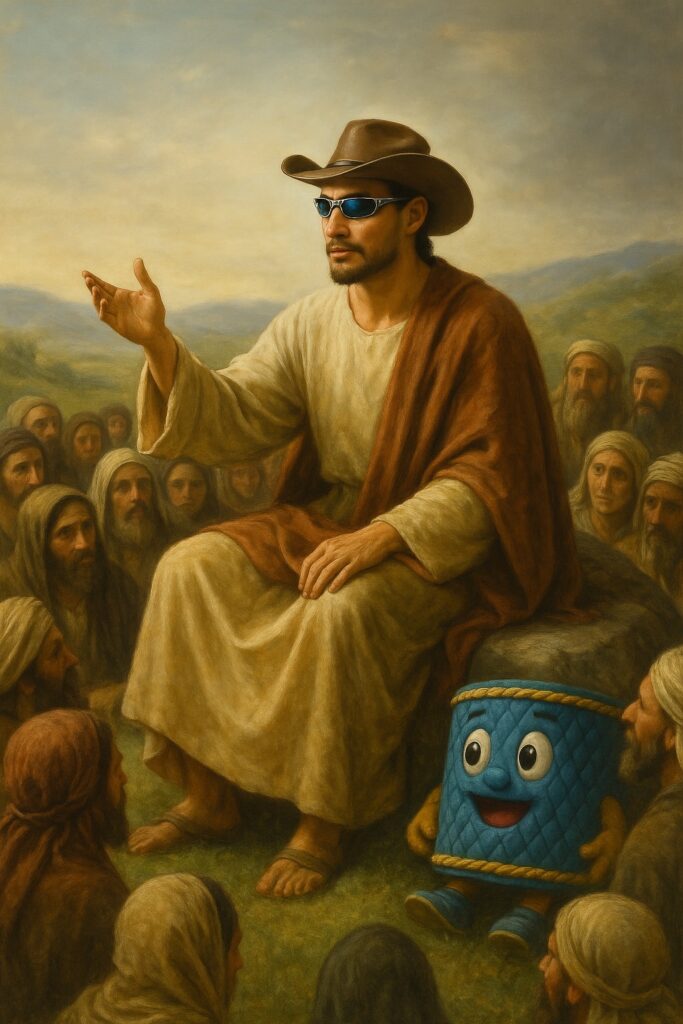
私が最初に手をつけたのは、予定表の作成でした。
休みの人の確認、当日の製造予定と製造数の共有。
その上で、私自身の考えや思考、目標、小話を交えてモチベーションを共有し、意識を一つにすることを試みました。
さらに、職場に根づく悪癖や陰口、愚痴を正す道徳的な話。
そして最後に、「今日という日にどう向き合うか」という心構えを伝える時間に変えていったのです。
その変化は、現場にも明らかに表れました。
情報が円滑に伝わるようになり、納期への対応も迅速に。
私は管理職として現場にも積極的に入り、誰よりも製造に携わることで、情報のハブとなりました。お客様のニーズを正確にくみ取り、製品に反映し、技術として表現する。それが信頼を生み、職人たちからの尊敬を得ることにもつながりました。その信頼感は、今の朝礼の在り方にも反映されていると思います。
今では、朝礼は「みんなのもの」になりました。
私はその役目を、管理職や総合職の社員へと譲りました。彼らは予定表を確認しながら指示を出し、3分間のスピーチを通して倫理観を共有し、自分自身も文章を書くことで成長していきます。
聞く側の社員たちも、そのたった3分に詰まった濃密な話に心を動かされる。
そしてラジオ体操を終え、それぞれの持ち場へ向かう。
朝礼はもはや、単なる連絡事項の場ではありません。
学びの場、発見の場、成長の場、そして「同じベクトル」を共有する大切な時間へと進化してきました。
そして今年――その朝礼はさらに進化しようとしています。
今度は、一般職や職人さんが、交代制で朝礼の司会に挑戦することになったのです。
人前で話すのが苦手な人もいる。文章を書くのが苦手な人もいる。
それでも、私は知ってほしいと思います。
誰しもが、人に語るとき、文章を書くとき、大きな勇気と苦労を抱えているということを。
そして、言葉とは、自分に返ってくるものであるということも。
言葉は、人を傷つけ、押しつぶすこともできます。
でもその同じ言葉で、人を癒し、励まし、奮い立たせることもできる。
言葉は、自分が選ぶもの。
朝礼を通して、それを心の底から実感してほしいのです。
私たちは意識しなければ、つい楽な方、悪い方に流されてしまう弱さを持っています。
だからこそ、自分を律し、善い生き方を選び取っていく力が求められているのです。
「礼に始まり、礼に終わる」
これは武道に限らず、日本人の生き方そのものだと、私は思っています。
礼とは、単なるあいさつではありません。
それは心の表れであり、教えであり、生きざまの体現でもあります。
だから、礼をするとき、私は自分に問いかけるのです。
― 相手を本当に尊敬しているか?
― 相手の人生を大切に思っているか?
― 自分ひとりで生きていると勘違いしていないか?
礼が必要なのは、人が弱く、孤独に生きられない存在だからです。
それでもなお、自尊心を持って、魂を一段高めていこうとする意志が、そこにはあります。
私たちは、家族と、仲間と、そして向き合う相手と共に、大きく成長し、羽ばたいていく。
相手を敬い、報い、讃え、感謝する――
人生の終わりもまた、そうであるべきだと、私は思うのです。
それが、先人たちが私たちに伝えてきた「礼」の本質ではないでしょうか。